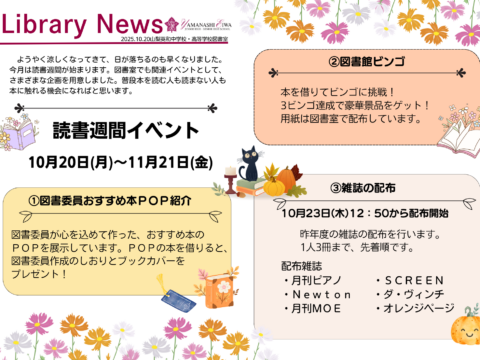第2回大学模擬授業を実施しました
10月10日(金)高校1.2年生を対象とした2回目の大学模擬授業を行いました。
今回は、人文学、心理学、語学・国際学、教育学、生命環境・農学、服飾・被服学、芸術学、看護学、経済・経営学の9分野の授業を開講しました。これで、今年度の大学模擬授業は終了です。新たに興味のある分野に出会えた人、進路決定のきっかけを見つけた生徒もいると思います。この貴重な授業で得た知識を、日々の学習や生活に生かしていってほしいと思います。熱意ある講義をしてくださった先生方へ、心より感謝申し上げます。
~第2回大学模擬授業 開講授業タイトル~
*人文学 ことばの選択について:バイリンガルからの視点
*心理学 乳幼児の精神発達の基盤について
*語学・国際学 ことばと文化:英語を通して異文化理解の旅に出よう!
*教育学 のぞいてみよう子どもの世界
*生命環境・農学 国内における水辺環境の現状と保全について
*服飾・被服学 多彩な服飾・被服学の世界
*芸術学 現代アートとは何か?音楽と美術の横断的表現
*看護学 知っておきたいファーストエイド(救急処置)
*経済・経営学 人々の well-being(幸せ)と経済
~生徒感想~
*人文学
この講義を通して、コードスイッチングが単なる言語の混ざりではなく、バイリンガルの柔軟な思考や高い言語能力を表す現象だと学びました。これまでオンライン英会話や海外交流を通して、相手や場面に応じて自然に言葉を選ぶことの大切さを感じてきました。今回の学びでその背景にある理論を知り、より深く理解できました。言語は文化や価値観を映すものであり、使い方で人との関係、雰囲気を変える力があると思います。言語学や国際関係学に興味が深まり、言語を見る視点が広がったと感じました。将来は、言語学や国際的な分野で多言語を通して人をつなぐような仕事に関わりたいと再確認できました。(高2)
*心理学
子供の精神的な発達などについて、わかりやすく興味深い講義で学ぶことができました。様々な実験動画などで子供の心身の発達などについて詳しく知ることができました。中でも、ボウルビーの研究であるホスピタリズム研究が興味深かったです。親と離れて施設で暮らす子供たちの精神的、身体的な問題が、複数の保育士で面倒を見ていることが原因であったということに驚きました。困ったときに必ず助けてくれる、特定の頼れる「安全基地」の存在が、子供の成長や発達に非常に大きな影響をもたらすのだということを知ることができました。心理学にたくさん触れてみたいと思いました。(高2)
*語学・国際学
今回の講義で学んだことは、言語は単にコミュニケーションツールにとどまらず、思考や物の見方を形作るものであるということです。私は、言語は言葉を伝えたり意思疎通を図る上で大切な物であると考えていました。しかしそれ以外にも言語は人々の価値観にも影響を与えていることがわかりました。そして今回の講義で気がついたことがあります。それは外国語を学ぶ上で大切なのは、まず母国語を理解することということです。母国語を深く理解することによって、自分の考えを正確に表現できるようになり、他の言語との違いもより明確に感じ取ることができます。言語の背景には、その国の文化や歴史、人々の価値観が反映されているため、自分の言葉を理解することは、自分の文化を理解することにもつながると思いました。今回の講義を通して、言葉は単なる道具なのではなく、私たちの思考を形づくるものだと思いました。これからは、母国語と外国語の両方を大切にしながら、言葉の持つ力を意識して使っていきたいです。(高2)
*教育学
模擬授業を受けて、改めて先生の素晴らしさを実感したと同時に、やはり大変なお仕事なのだとわかりました。家庭科で学んだ幼稚園や保育園、子ども園の違いを再度確認できましたが、最近増えてきているこども園の先生になるためには、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方を持っている必要があると知り驚きました。また、一種と二種と専修の違いにも触れていただき、想像がしやすかったです。一番印象に残ったことは、絵本の読み聞かせです。パンどろぼうを読んでいただいたのですが、一冊の中に先生の技術が全部つまっていて思わず没頭してしまいました。物語がゆっくり流れ、最後に近づき落ち着いている場面ではページを捲るスピードを遅くしたり、緊張感があり、聞いているみんながドキドキする場面では早く捲るそうです。「本の世界を提供してあげる」ための工夫がたくさんあってとてもかっこよかったです。また、本に書いてある小さい文字にも触れていたり、登場人物によって声を変えていたりと本当に圧倒されました。入園時は何もかも先生がやっていたのに、卒園する時には一人でできるようになっている、その著しい成長を見ることができる、とおっしゃっていたことも心に残っています。今回の授業を受けて、子どもの成長を助ける先生というお仕事の大変さと大切さを知ることができ、本当に良かったです。(高2)
*生命環境・農学
自分がやりたい研究とは違う分野でしたが、とても興味深く面白い講義で、90分があっという間に感じられました。地形や環境を通してそれぞれの場所に適応し繁殖する水草は、保全するのがとても難しいことを知りました。また自分は、水草は汚いところに生えているようなイメージもあったので、水草が環境を綺麗にしている大きな鍵となっていることにとても驚きました。防波堤などで壊されてしまった環境が多くあることも初めて知り、どうしたら安全に暮らせ、さらに環境も守っていけるのかをもっと考えてみたいです。(高2)
*服飾・被服学
服の型紙の膨らみは円錐の形をもとに作られていると知り、驚きました。服飾とは、社会学、心理学などにも関係しており、服を作ることだけではないのだと思いました。ファッションショーの動画を見せていただいた時、学生さんが作るそれぞれの世界観の服がどれも素敵で心が高鳴りました。ファッションは私を夢の世界へ連れていってくれるものなのだと改めて思いました。今回の授業を受けることができ、とても嬉しかったです。ありがとうございます。(高1)
*芸術学
芸術系の模擬授業は受けたことがなかったので、授業の雰囲気や、普段どのようなことをしているのかを知る機会となり、とても新鮮でした。作品についての話では、見たことのある作品でも、作者が何を思って描いたか、作曲したかを新しい視点で解釈することの面白さを感じることができました。また、音楽に関してはあまり考えたことがなかったのですが、講師の方のお話を聞いて新しく興味も湧きました。普段私たちが持っている先入観は大切ですが、それを壊して考えることも大切であり、面白く感じました。大学を決める際にも、自分の常識を一度取り払って考えてみたいと思いました。一つのジャンルに絞ろうと思わず、もっとユニークな発想で物事を考える大切さを知る機会となり、本当に参加して良かったと思いました。(高1)
*看護学
今回の模擬授業を受けて、私は「看護=病院の中だけの仕事」だと思っていた考えが大きく変わりました。災害時や事故の現場など、いつどこで人の命が危険にさらされるか分からない中で、看護師は冷静に判断し、限られた状況の中でも最善を尽くす力が求められることを学びました。特に印象に残ったのは、「まず自分を守ることが、結果的に他人を助けることになる」という考え方です。私は今まで、“人を助けるためには自分を後回しにしなければいけない”と思っていたけれど、先生の話を聞いて、その考え方が少し変わりました。もし自分が倒れてしまったら、助けられるはずの人も助けられなくなってしまう。だからこそ、どんなときも落ち着いて状況を見て、自分の身を守る判断ができるようになることが大切だと思いました。これからの生活の中でも、災害時の避難経路を確認したり、応急手当の知識を少しずつ身につけたりして、自分や周りの人を守れるようになりたいです。そして、看護師を目指す上で、ただ知識を覚えるだけでなく、いざという時に“行動できる力”を身につけることを目標にしていきたいと思いました。(高2)
*経済・経営学
今回の授業を通して、経済というものの見方が大きく変わりました。これまで「経済=お金の流れ」だと思っていましたが、実際には「人々の幸せをどう実現するか」という目的のための仕組みであることを知り、とても印象に残りました。特に、「効率的であること」と「公平であること」の両立が難しいという点に深く考えさせられました。どちらか一方だけを重視すると、社会の中で取り残される人が出てしまう可能性があることを知り、経済のバランスの大切さを感じました。また、幸福がGDPなどの数値だけで決まらないという話も印象的でした。自分の身の回りを考えてみても、物がたくさんあっても満たされないときがある一方で、人とのつながりや安心できる環境があることで幸せを感じる瞬間があります。経済は、単に「豊かさ」を生み出すものではなく、「どうすれば多くの人が幸せに生きられるか」を考えるためのものなのだと理解しました。これからニュースや社会問題を見聞きするときも、「誰が幸せになっているのか」「誰が取り残されているのか」という視点を持ちたいと思いました。経済学は難しいものだと思っていましたが、人々の生活や幸せと密接に関わっている身近な学問だと感じました。(高2)